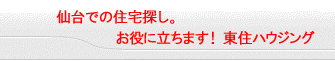- 騒音について
-
昼間はそれほど気にならない音でも、夜になると思いのほか響くことがあります。特に夜間(10時以降)はトラブルが起きやすいので、生活音や騒音は気づかずに出していることが多いものですが、常に配慮するよう心がけてください。
● AV機器・カラオケなどステレオや楽器・テレビ・カラオケなどは、時間帯や音量に気をつけて楽しむのがマナー。特に夜間はボリュームを下げるか、ヘッドホンを使用するなどして配慮しましょう。
※ ピアノの持ち込みは原則として禁止です。音以外にも床に過度の荷重がかかるため危険です。● 生活音玄関ドアや建具などは静かにゆっくり閉めましょう。また夜間の水の使用音はよく響きますので、この時間帯はできるだけ入浴・洗濯・掃除は避けるようにしてください。
● 会話会話の声は、特に夜間の大声は両隣に漏れ聞こえやすいものです。充分配慮しましょう。
● 衝撃音飛び跳ねたり、物を落としたときの床の衝撃音は、上下階とのトラブルの原因となります。特に小さなお子様がいるご家庭では、防音対策をお願いいたします。

● 車エンジンの空ふかしやクラクションをむやみに鳴らさないようにしましょう。
- ゴミの出し方について
-
ゴミの処分は、収集方法・収集日・分別方法その他について、地域によってルールが異なりますので、必ず管理会社か市町村へお問い合わせのうえ、指定された日時・場所・方法とマナーを遵守して出してください。ルールが守られていない場合、ゴミの所有者の調査・処分代行費の請求・ゴミ置き場の利用禁止などの対処をさせていただく場合がありますのでご注意ください。
● ゴミの処理はマナーを守って、自己管理で
- ゴミは必ず決められた収集日時に合わせて出しましょう。収集日の前日に出すなど、早出しは控えてください。
- 指定のゴミ袋がある場合は、必ず使用してください(指定外のゴミ袋は回収されません)。
- 収集時間に間に合わなかったゴミは必ず持ち帰りましょう。
- ゴミが散乱しないよう、袋の口をしっかり縛って出してください。
- 個人情報が含まれるゴミは各自の責任で十分に注意して処分してください。
● 粗大ゴミは要注意粗大ゴミは各市町村に連絡し、決められた方法で処分してください。粗大ゴミを指定日・方法以外で出すと不法投棄とみなされて罰せられたり、処分費用を請求されたりする場合があります。やむをえず、指定日以外に出したい場合には、市町村に連絡して引き取ってもらうようにしましょう。

- 共用部分について
-
共用部分は、ご入居者全員が活用できるスペースです。ご入居者同士のトラブルを回避するためにも、ルールをしっかり守って使用するよう心がけてください。また、快適性や建物の美観を守るために、常に清潔保持・整理整頓を心がけることも大切です。
● 駐車について違法駐車はご入居者の方だけでなく、近隣の皆様にも迷惑がかかりますので、以下の禁止事項が守られない場合は解約を申し出る場合があります。
- 他人の駐車区画・近隣道路および出入り口付近など、所定駐車スペース以外での駐車
- クラクション・空ふかし・長時間のアイドリングなど、他人に迷惑を及ぼす行為
- 多量もしくは長時間にわたる荷物の積み下ろし(引越し時は除く)
- 駐車場を自動車の駐車以外の目的で使用すること
- 駐車場に自転車やバイク、ベビーカーなど、自動車以外のものを置くこと
- 駐車場を営業用もしくは来客用駐車スペースとして利用すること
- マフラーの改造車および暴走族のバイクや車、駐車スペースに収まらない車(トラック、改造四駆など)の駐車
- 駐車場内でお子様を遊ばせること

駐車場での自動車の保管上もしくはご利用者同士のトラブルについては、各契約者の責任となり管理会社は一切責任を負いません。盗難、損傷などの事故には十分注意してください。また、盗難防犯装置のアラーム感度は、隣接車のドアの開閉に反応しないよう、低めに設定してください。
● 駐輪について自転車・バイクは、決められた場所に置いてください。また使用しない自転車・バイクは放置せず各自で速やかに処分してください。なお、使用されていない壊れた自転車やバイクなどは、警告後に管理会社が処分する場合があります。駐輪場での盗難、損傷などの事故については貸主および管理会社は一切責任を負いません。また物件によってはバイクの駐輪をお断りすることがあります。(大型バイクの駐輪は事前に許可が必要です)。
● 廊下・階段階段・踊り場・廊下などは共用スペースですので、私物やゴミなどの不用品を放置してはいけません(消防法で禁止されています)。また、これらのスペースは緊急時の避難経路にもなります。大きな物を放置していると災害避難時の通行の妨げになり、大変危険です。
● 浄化槽浄化槽は使用規定に基づきご利用ください。また、異臭や異常音がしたら、すぐに管理会社にご連絡ください。
● 専用庭専用庭の管理(除草作業など)はご入居者にてお願いいたします。
● 電灯共用部の電灯の球が切れている場合は、管理会社にご連絡ください。
- ペットの飼育禁止について
-
最近は、ペットの飼育が可能な物件も増えてきていますが、大多数は鳴き声や衛生上の問題から契約書で禁止されています。その場合は室内外ともに、飼育はもちろん一時的に預かることもできませんのでご注意ください。ペット飼育可能な物件では、ペット飼育規定を十分ご熟読のうえ、他のご入居者に迷惑がかからないよう配慮をお願いいたします。なお、すべての物件において、敷地内・隣接地・隣接道での犬猫などの餌づけ行為は禁止されています。
- 表札について
-
表札は、入居後すぐに玄関ドアと集合郵便受け(ある場合)の所定の位置に、姓名を表示してください。表示されないと、郵便物が届かない場合があります。なお、営業用の表示・姓名以外のシールやポスターの貼付は禁止されています。
- 建物の維持管理への協力
-
管理会社は、ご入居者の方に安全にお住まいいただくために、建物の維持管理を行います。そのため、室内の住宅用火災警報器の機能点検など、住戸内への入室が必要な場合がありますので、管理会社よりそのような申し出がありました場合には、ご理解とご協力をお願いたします。
- エアコン室外機の設置について
-
2階以上の居室のご入居者は、バルコニーに設置してください。バルコニーがない場合は、1階に設置する場合があります。その際は、事前に必ず管理会社と設置場所などについて相談してください。
- 湿気の防止と換気について
-
湿気を防ぐために、晴れた日には窓を開けて通風をよくし、押入れの襖やクローゼットの扉も開放しましょう。水蒸気の多い浴室・キッチンでは、窓を開けて換気扇を回すなど十分な換気が必要です。建物に24時間換気システムが設置されている場合は常時運転しておきましょう。
● 湿気の影響と対策
- 押入れは下にスノコを敷き、空気が対流しやすいようにしてください(乾燥剤などを利用するのも効果的です)。
- タンスなどの家具は、壁面より5cm程度離し、家具の裏面も通気されるようにしましょう。
- 通気口およびサッシの上部に換気框がついている場合は開けておいてください。特に24時間換気の通気口の表示がある場合は、必ず開けておきましょう。
● カビの発生について日本は、高温多湿という気候上、カビが発生しやすいため、梅雨の時期や長期の不在におけるカビの発生(特に畳)には、十分注意してください。
- 結露の防止について
-
結露は、室内外の温度差が大きいときに、高い温度側の空気に含まれる水蒸気が、冷たい面に触れて水滴になったものです。建物の断熱性・機密性が高いため、冷暖房の効率がよい反面、換気をしないと室内で発生した水蒸気がこもり、結露が発生する原因となります。結露はカビの発生源になるだけでなく、建物や家財を傷めますので、換気設備や冷暖房設備を利用して、室内環境を適切に維持しましょう。結露が発生しているにもかかわらず、対策を怠り、カビ、シミなどが発生した場合、ご入居者の責任となり退去の際に補修などの費用が発生しますのでお気をつけください。結露の原因となる水蒸気の発生には、次の要因が考えられます。使用時は十分な換気をして、室内の湿度を適切(40~60%程度)に保つようにしましょう。
- ・ 調理・炊飯
- ・ 洗濯機、乾燥機
- ・ 風呂、シャワー、洗面
- ・ 室内園芸、花瓶、水槽
- ・ 加湿器
- ・ 室内で洗濯物を乾かす
- ・ 喫煙
- ・ 開放型燃焼器具(ガス・石油ストーブなどの使用が禁止されている場合があります。)
● 結露の影響と対策前述の湿気対策とともに、以下についても心がけてください。
- サッシや窓ガラスについた水滴は、こまめに拭き取ってください。
- 暖房中は部屋どうしの温度差をあまりつけないようにしてください。
- 室内に洗濯物を干すことは、結露だけでなくカビの原因にもなるので、湿度の高いときはなるべく控えてください。
- 雨天や多湿時など、換気で湿度を調整できないときには、エアコンの除湿運転や除湿器を利用して調整するようにしてください。
- 凍結の防止について
-
温暖な地域でも冬期は、水道管および風呂釜・給湯器内の水が凍結することがあり、機器の破損や水漏れの原因となります。凍結の可能性がある場合や長期間使用しないときは、以下の点にご注意ください。
● 冬期は水道の水抜きをこまめに寒冷地などで水抜き栓を設けている物件で、夜間あるいは外出などで長時間水道を使わないときは、凍結を防ぐために水抜き栓で水を抜いてください。水抜き作業を怠り、機器が破損した場合の補修費は、ご入居者の負担となりますのでご注意ください。
● 凍結防止ヒーターの電源を切らない給湯器の凍結防止ヒーターが作動しなくなると、給湯器が凍結破裂する恐れがあります。冬期は、凍結防止ヒーターの電源およびブレーカーは切らないでください。また凍結シーズン前には、コンセントプラグがきちんと差し込まれ、電源ランプが点灯しているか点検しておきましょう。万一、給湯器が凍結破裂を起こした場合にかかる補修費用は、ご入居者の負担となりますのでご注意ください。
- 水もれの防止について
-
基本的に浴室以外は防水工事をしておりませんので、水をはじめ液体を床にこぼすと水もれを起こす恐れがあります。階下に迷惑をかけるだけでなく、損害賠償の負担も生じますのでくれぐれもご注意ください。室内で水もれが起きた場合には、上下階の水の使用状況と漏水状況を確認し、管理会社にご連絡ください。
- 浴室や洗濯機に水を入れたまま外出しないようにしましょう。
- トイレのタンク内洗浄剤は便器の表面を傷つけ、詰まり、漏水の原因になります。ご使用はお避けください。
- 洗濯機の排水ホースは、排水口にしっかり固定しましょう。また、エアコンの排水ドレン管は、2階以上の場合は、地上まで下げるか、バルコニーの排水口に直接排水できるように設置してください。
- 浴室、キッチンなどの排水口を定期的に清掃し、水があふれ出ないようにしましょう。
- 全自動洗濯機など、給水ホースを蛇口に取り付け自動で給水を行うものは、洗濯機使用時以外は蛇口を必ず閉栓してください。水圧で給水ホースが外れ、階下への水漏れの原因となります。
- バルコニーは防水処理していませんので、植物への散水時などは、水の扱いや排水口の泥詰まりに注意しましょう。
- 喫煙について
-
壁紙などに付着したタバコのヤニ汚れは、クリーニングしてもほとんど落ちません。また、タバコを床に落として焼けこげ、さらには火事につながる恐れもあります。汚れがひどい場合、そして損傷・損害が発生した場合、原状回復や損害賠償にかかる費用はご入居者の負担となりますのでご注意ください。
- 換気扇・エアコンの掃除について
-
換気扇やエアコンの汚れは、放置しておくとこびりついてしまい、お掃除が困難になってしまいます。また運転効率が下がるだけでなく故障の原因にもなります。こまめなお掃除を心がけてください。
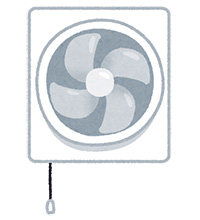
- エアコンフィルターの掃除は季節替わりに
-
冷暖房のエアコンのフィルターは、熱交換器に入る前の空気の汚れ(タバコのヤニなど)を取るものなので汚れがすぐにたまります。お掃除はフィルターを外し水洗いや電気掃除機で行ってください。汚れがひどいときには、洗剤をスプレーしてブラシで洗ってください。
- 換気扇の掃除は3ヶ月に1度が目安
-
換気扇は空気と一緒に油分も吸い込むので、油と汚れでベトベトになってしまいます。お掃除は必ずゴム手袋をして電源を切り、換気扇を取り外して行いましょう。
- 設備機器の取付けについて
-
管理会社の承諾なく、電源やスリーブの新設・個別アンテナの設置などは行わないでください。エアコンは専用コンセントや壁の補強のある指定場所に設置しましょう。エアコン用の電源や配管用スリーブは既設のものを利用してください。
- 鍵の管理について
-
鍵の取り扱いには細心の注意を払い、合鍵を作ることはやめましょう。もし鍵を紛失した場合には、すぐに管理会社にご連絡ください。その後、防犯のために原則として鍵シリンダーも取り替えますが、他業者には依頼せず、必ず管理会社に対応してもらうようにしてください。特に共用玄関にオートロックを採用している場合には、他業者に依頼した場合、共用玄関が開けられなくなります。なお、費用はご入居者の負担となります。
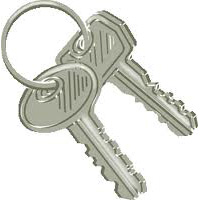
- サッシの防犯機能
-
クレセントの側面には上下式のダブルロックが付いています。クレセントとともに閉めておきましょう。また、サッシにはクレセントの他に、下部に補助ロックが付いている種類もあります。クレセントだけでなく補助ロックも掛けておくと、外部からの侵入に対していっそう安心です。
- ウインドアームの活用
-
玄関ドアには、ドアチェーンと同じ機能を持つウインドアームが付いています。初対面の人へは、まずウインドアームを掛けて応対し、防犯に役立ててください。
- 雨戸の活用
-
窃盗犯の場合、ガラスを割って家の中に侵入するケースが多くみられます。雨戸がある場合には、外出時に必ず雨戸を閉めるように心がけましょう。
- 振込め詐欺・訪問販売の対応について
-
集合住宅は、ダイレクトメールや訪問販売・各種勧誘などのターゲットになりやすいものです。なかには詐欺まがいのものや正規代理店や行政機関を装うなど、悪質な業者も存在しますので、安易に信用せず、慎重な対応を心がけてください。また被害を受けた場合は、速やかに警察へ通報するとともに、管理会社へもご一報ください。管理会社の名前を用いて「賃貸料の振込先が変更になりました。今後は下記の銀行口座にお振込みください」という内容の通知文を配布し、賃貸料をだまし取る事件が発生しています。不審な文書や案内を受けた場合には、必ず管理会社に問い合わせてください。また被害を受けた場合には、速やかにお知らせください。管理会社から訪問販売の依頼や斡旋は一切しておりません。「管理会社の了解を得て~」など、不審な業者が訪問したときは、管理会社までご確認ください。

- もし被害にあったら...
-
万一、盗難などの被害を受けた場合、管理会社に対して損害額の賠償請求はできません。ただし泥棒など加害者に対しては、もちろん損害額を請求できます。

- 地震
-
<日常の心構え>
● 習慣として身につけたいこと- 家族が落ち合う場所を前もって決めておく。
- 地区によって指定されている避難場所の位置と道順を確かめておく。
- 浴槽の残り湯(1/3程度)を捨てない(断水の場合もトイレなどに再利用できますが、幼児のいるご家庭では溺水事故の危険がありおすすめできません)。
- 飲料水・非常食の確保(ペットボトル・カンパン・チョコレート・ビスケット・缶詰類)。
- 停電の場合の備え(懐中電灯やラジオ・小銭)。
- 防寒・防災グッズの備え(ヘルメット・厚手の靴下・防寒具類)。
- 各種設備などの取り扱い方を知る。
● その他、日頃から準備しておきたいもの
- 貴重品や、子どもの日常品をまとめたバッグ(両手が自由に使える、リュックサック類がよいでしょう)
- 携帯用のガスボンベ・ガスコンロ
- 毛布・マフラー類
- 電話帳・小銭(安否を気づかう電話で回線がパンク状態になるため、公衆電話が一番便利です)
- 医薬品(外傷手当)・生理用品類
- 簡単な日曜大工セット
- オートバイ・自転車類(自動車はあまり役に立ちません)
● 窓際にものを置かない特に手すりの柵に植木鉢などを置くと、何かの拍子で落ちる恐れがあり、大変危険です。
● 家具の上にはなるべくものを置かない地震の際、家具の上に置いたものが落下してケガをする恐れがあります。また、2段重ねの家具は外れて落ちたり倒れたりしやすいので、市販の固定金具で家具どうしを固定するなどして対策をしておきましょう。
<地震が起きたら>
地震はいつ発生するか予想できないだけに、グラッときたらまず身の安全を図ることが大切です。揺れがおさまるのを待って状況判断をしてください。大きな地震のあとには、必ず余震がありますので落ち着いて行動しましょう。● あわてて外へ飛び出さない丈夫なテーブルの下などに身を隠し、揺れがおさまるのを待ちます。頭を座布団などでしっかり保護しましょう。
● 真っ先に火の始末を揺れがおさまったら、まず火の始末を。コンロはもちろん、石油ストーブなどは特に要注意です。電気器具はスイッチを切り、コンセントも抜いておきましょう。ガスの元栓を閉めるのも忘れずに。
● 戸外では広いところを通って避難するブロック塀のそばや狭い路地は危険です。また、電柱が倒れてくる場合がありますので、頭をしっかりガードしておきましょう。
<地震のあとは>
● 建物や設備の傷みを点検給排水管の漏水やガス漏れ・電気系統の異常・建具の開閉などをチェックしましょう。他にも屋根瓦のズレ、基礎・外壁の亀裂などを発見した場合は、管理会社にご連絡ください。 - 雷
-
<雷が鳴りだしたら>
● 室内では、部屋のまん中にいれば安全です鉄骨住宅は落雷が心配されがちですが、金属材料を使った建物は中にいる人間を完璧に守ってくれます。いかに大きな落雷であっても、電流はすべて鉄骨の中を通って地中に流れ、部屋の中にいる人間が感電するほどの電位差(電圧)は生じません。落雷があっても、部屋の真ん中にいればより安全です。● 雷が激しいときには、電気設備機器の対策が必要です近くに落雷があった場合、一時的に電圧が変わり機器を傷めることがあります。まず、テレビからアンテナ線をはずし、設備機器などの差込みプラグを抜いておきましょう。
● 給湯器や暖房便座など、微電流を使った設備機器の差込みプラグも必ず抜いておきましょう
<落雷したら>
● 分電盤を確認しましょう落雷によってブレーカが落ち、停電することがあります。分電盤をまず確認しておきましょう。● 直撃雷でなくても被害を受けることがあります電柱や電線近くに落雷した場合、電線に瞬間的に高電圧の電流が流れ(誘導雷)、機器類のマイコンなどに損傷を与えることがあります。機器類が正常に作動するか、点検しておきましょう。
- 火災
-
<日常の注意点>
● 引っ越しをしたらすぐ非常ベル、非常階段、避難経路の確認をしましょう● タバコの火の始末はきちんとしましょう。
● お料理中にコンロから離れるときは火を消してから
● 開放型燃焼器具の使用について火災を防ぐため、賃貸住宅によっては開放型燃料器具(石油ストーブ、ガスストーブ)の使用を禁止している場合があります。
● 給湯器やガス機器の周りには、燃えやすい物を置かないでください
● 住宅用火災警報器などを確認しておいてください寝室・キッチンの天井に住宅用火災警報器が付いています。取扱説明書に従い、定期的に点検し作動を確認してください。製品寿命(約10年)が近づくと警報音が小さく鳴りますので、機器の交換を管理会社に申し出るようにしましょう。
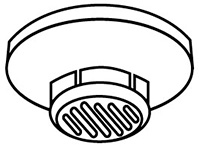
● 避難方法を日頃から考えておきましょう避難の邪魔になるので、廊下や出入り口には荷物を放置しておかないこと。玄関以外の避難口も考えておきましょう。
<火災が起きたら>
● まず家族や近所に知らせて119番を大声や大きな音で、周りに火災を知らせましょう。消防署への通報は、場所・目印の建物・火災の様子・ケガ人の有無などを要領よくはっきり伝えましょう。● 初期消火をおこなう小さな火災であれば、状況を判断し、自分で消火できる場合があります。ただし、何でもむやみに水をかけるのは間違いです。
- 油ナベが火元の場合
あわてて水をかけるのは厳禁。消火器がないときは、濡らしたシーツや大きめのタオルなどを手前から覆うようにかけ、空気を遮断して窒息消火します。 - 電化製品が火元の場合
いきなり水をかけると感電の可能性があり危険です。消火器がないときは、ブラグを抜いてから(できればブレーカーも落とす)、水で消火します。 - カーテンや襖が火元の場合
火は上に広がりやすいので、天井に移る前にカーテンは引きちぎり、襖は蹴り倒してから消火器・水などで消火してください。 - 石油ストーブが火元の場合
真上から一気に水をかけます。石油がこぼれて広がっていたら、毛布などで覆ってから水をかけて消火します。
● 消火器の使い方
- 消化器の安全栓を引き抜く
- ノズルを火元に向ける
- レバーを強く握る
- 燃えているものに向かって薬剤を噴射する

● 消火器の置き場所容器が腐食したり薬剤が変質したりする恐れがありますので、置き場所にはご注意ください。
<適さない場所>- ・水がかかったり湿気の多いところ
- ・直射日光のあたるところ
- ・熱が直接本体にあたるところ
- ・倒れる恐れのあるところ
- 油ナベが火元の場合
- 台風
-
<台風の接近時>
● テレビやラジオの台風情報に注意予報はたびたび修正されますから、1回だけの情報で判断するのは禁物です。● 床下・床上浸水の可能性がある場合には、ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを切っておきましょう
● 戸締りのチェックを忘れずに各部屋を見回り、雨戸がある場合は雨戸を施錠し、窓を閉めてクレセント錠を掛けます。ガタツキ止めロックのある雨戸は、必ずロックしましょう。
<通過後の点検>
● 飛来物のお掃除、建物の傷みのチェックを屋根や外壁・ベランダ・雨戸・サッシなどに傷みやキズがあれば、管理会社にご連絡ください。また、排水路の詰まりを見つけられましたら、取り除いてください。 - 積雪
-
<積雪期前のチェック>
● 積雪期の前後は前もって点検しておきましょう積雪シーズンの前後は、屋根や外まわりの点検をしておきましょう。出入口などの除雪は、各自入居者様が協力して行ってください。● バルコニーに雪をためないようにしましょうオーバーフロー管や排水溝が雪で塞がった状態で雪が解けると、バルコニーに水が溜まってあふれ、室内に水が流れ込む恐れがあります。
- 水まわり
-
Q1. 子どもがトイレの錠を誤って中から掛けてしまった・・・
A1.ドアの外側の錠穴を、コインなどで回すとロックが解除され、ドアを開けることができます。
Q2. 水洗トイレが詰まったら?
A2.水をためた状態で便器の排水口にラバーカップ(吸引用具)を密着させ、静かに押付けて勢いよく引く、という動作を繰り返すとたいていの詰まりは取れます。ラバーカップを使用するときは、便器を透明のビニールシートで覆い、汚水が飛び散るのを防ぎましょう。ラバーカップはDIY店(ホームセンター)で販売されています。
Q3. 水洗トイレの水が流れなくなったり、止まらなくなったら?
A3-a. 水が流れない場合
ロータンク内の排水弁を動かす鎖が、引っかかっているか切れていて、排水弁が開かなくなったと考えられます。ロータンク内を調べ、鎖が切れていたら応急処置としてビニールひもなどでつないでおき、早めに管理会社にご連絡ください。A3-b. 水が止まらない場合
排水弁の劣化や、排水弁と排水口との間に砂やゴミが挟まって、しっかり閉じていない可能性があります。ゴミを取り除き、排水弁に劣化やキズがある場合は取り替えてください。また鎖がよじれて排水口を塞げなくなっている場合、一旦鎖をはずして少したるむ程度に掛け直してください。
それでも止まらない場合は、応急処置としてロータンク下の止水栓をドライバーで回して閉じます。それから管理会社までご連絡ください。
Q4. キッチンや洗面台・お風呂・洗濯機の排水口が流れにくかったり、詰まったら?
A4.流れにくさ・詰まりの主な原因は、キッチンは油や生ゴミ、洗面台やお風呂は髪の毛、洗濯機は糸クズなどです。いちばんの対処法は、こまめなお掃除です。1カ月に1度は行いましょう。キッチンや洗面台が詰まってしまったら元栓を閉め、トラップの下に汚水を受けるバケツを置き、トラップのネジをはずして内部に詰まったゴミを取り除いてください。お風呂・洗濯機の排水口はベル型の場合、目皿を外して異物やゴミを取り除いてください。
Q5. キッチンや洗面台の水栓のハンドルを締めても水が止まらない場合は?
A5.応急処置として、止水栓を閉じてください。洗面化粧台、キッチンの場合はキャビネット内の手元止水栓で止めます。止水栓のない水栓(洗濯カランなど)の場合は、各々の屋外水道メーターボックス内にある元栓を閉めてください。それから管理会社までご連絡ください。
Q6. 水道管から水漏れしていたら?
A6.すぐに水道メーターボックス内の元栓を閉めます。2階の場合には、下に漏れる恐れがありますので、すぐに拭きとってください。それから管理会社までご連絡ください。
- 電気
-
Q7. 停電でもないのに電気が切れたら?
※安全ブレーカ・漏電ブレーカのどちらが切れるかによって、原因と対処方法が異なります。
A7-a. 安全ブレーカが切れる場合- 切れた安全ブレーカ回路での電気の使い過ぎ
- 使用している電化製品が配線の短絡(ショート)により、過電流が流れている
- 建物側の電気設備の故障
以上の原因が考えられます。対処法としては、まず切れる安全ブレーカの回路のコンセントに接続されている電化製品のプラグを、すべて外してみてください。それでもまだ安全ブレーカが切れる場合は、建物側の電気設備(照明・壁内配線など)の故障の可能性が高いと言えます。すぐに管理会社にご連絡ください。
A7-b. 漏電ブレーカが切れる場合
これは漏電が起こったということです。
次の方法で対処してください。- 分電盤のブレーカを全部切ります。
- 漏電ブレーカを復帰し、安全ブレーカを1つずつ上げてください。
この方法で再び漏電ブレーカが落ちれば、その安全ブレーカの回路が漏電していることになります。他の回路の電気は使えますが、漏電した部分は至急修理する必要がありますので、管理会社にご連絡ください。
Q8. テレビの映りが悪くて困ったら?
A8.テレビがよく映らない……そんな場合はアンテナやテレビの故障、電波障害などが考えられますので、以下の点を確認しましょう。- 電源が、コンセントから抜けていないか?
- アンテナ(フィーダー・同軸ケーブル)は外れていないか?
- アンテナが倒れていないか?
- 外部にある共用電気のブレーカスイッチが下りていないか?
(共用アンテナ増幅器が設置されている場合には、電源が切れると増幅器が働かなくなります) - おとなりのテレビの映り具合(故障がテレビかアンテナかを判断できます)
- 地域によってVHFまたはUHFの受信が異なります
(転居前の地域と異なっている場合は、テレビ自体のチューニングをやり直す必要があります)
※電波障害の場合には、直らないことがあります。またCATVの場合は、当該会社の管轄担当にご連絡ください。
- ガス
-
Q9. ガスが急に出なくなった場合は?
A9.ガスのマイコンメーターには地震や流量異常などを感知する機能がついていますので、何かものが当たったためにガスが遮断された可能性があります。まずマイコンメーターのところへ行き、表示ランプが赤く点滅していれば、ガスは遮断されています。その場合には、下記の手順で復帰できます。その他の異常があった場合は、すぐにガス会社までご連絡ください。- すべてのガス元栓を閉める。
- 復帰ボタンのキャップをはずす。
- 復帰ボタンを強く押す。ランプの点灯を確認する。
- 手を離して2分間待つ(マイコンがガスの安全をチェック)。ランプの点滅が消えるとガスが使えます。
※長時間一定のガスを使用していると(煮物、ガスストーブなど)、マイコンメーターが働く場合があります。頻繁に止まる場合は、所轄ガス会社までご相談ください。
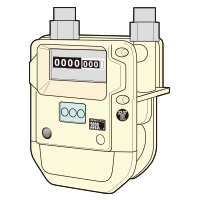
- その他
-
Q10. ガラスが割れたら?
A10.防犯上、応急措置のまま放置せず、至急管理会社にご連絡ください。
Q11. 玄関ドアの鍵を紛失したら?
A11.玄関ドアの鍵を紛失したら、とりあえずマスターキーまたは予備の鍵で解錠してください。その後、管理会社へ鍵のシリンダー交換を依頼してください。防犯上、合鍵を作るのは控えましょう。
Q12. 玄関ドアの錠(シリンダー)を交換するときは?
A12.錠はマスターキーに合うものが必要です。交換は必ず管理会社へご依頼ください。
Q13. 室内の住宅用火災警報器が、火災でもないのに鳴り続ける場合は?
A13.製品寿命が近づいていることや、故障をお知らせする警報音ですので、管理会社にご連絡ください。
Q14. 電動シャッターが停電などで止まってしまったら?
A14.スイッチによる操作はできませんが、手動で開閉することが可能です。モーター負荷がかかるため多少重くなりますが、できるだけシャッターの中央を持ってゆっくりと開閉してください。
Q15. 雷で電子機器の作動がおかしくなったら?(洗濯機・給湯器・エアコンなど)
A15.近所に落雷があったときなど、ショックで誤作動を起こし、正常な命令を受けつけなくなることがあります。正常な状態に戻すには、一旦、電流を遮断すれば回復します。コンセントを抜くか、分電盤の回路を切ってから再び入れ直してください。タイマーなどの設定が必要なものについては、機器の使用説明書を参考に、もう一度設定し直してください。電源を入れ直しても回復しない場合は、機器の故障と考えられますので、管理会社にご相談ください。
集合住宅のルールとマナー
集合住宅に住む人々は、一つの大家族のようなもの。おたがいが気持ちよく生活できるよう、常に配慮する姿勢が求められ、そして入居したその日から地域の一員となり、町内会・自治会などが定める地域のルールや慣習を守る義務が生じます。
快適な生活のために
住まいの空気の質や温度・湿度は、暮らしの快適感を大きく左右します。例えば、湿度が高いと不快なだけでなく結露でカビが生えやすくなりますし、換気扇やエアコンのフィルターが汚れていると換気効率が悪くなり、空気が汚れやすくなります。快適で健やかな生活のために、日頃から気をつけておきたいことを把握しましょう。
防犯のために
外出時はもちろんですが、油断しがちな在宅時は特に防犯の意識を持つことが大切です。在宅時は内側から鍵を掛け、知らない人が訪ねてきた場合はまずウインドアームを掛けた状態で応対しましょう。女性のひとり暮らしの場合は特に用心してください。また、日頃からご入居者どうしでコミュニケーションを取っておくことも大切です。
防災のために
2011年3月に起こった東日本大震災により、わたしたちは大自然の破壊力をあらためて認識させられました。日々の快適な生活も、常に地震や火災・台風といった災害の危機と隣り合わせです。いざというときに落ち着いて行動できるよう、安全対策をしっかり頭に入れておきましょう。
もしもの時のQ&A
賃貸住宅での生活で起こりがちなトラブルと簡単な対処のポイントを、Q&A形式で分かりやすくまとめました。基本的な知識を知っておくと、万一の場合にも応急処置を施すなど、適切に対処できますのでぜひご一読ください。その他お問い合わせ・ご相談は管理会社までご連絡ください。